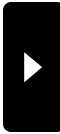写真はヤマ・ソービニオンに被せられた雨囲いです
雨はブドウ栽培にとって悩みの種です。
着実してから雨が降ると裂果といって実が裂けることがあります。
裂果は着実してすぐと、実が大きくなり色づきだしてからに起こり易いといわれています。
着実してすぐの裂果は裂けた実が自然に落ちて問題ありませんが、実が大きくなり色づきだしてからの裂果は他の実まで腐らすことがあり非常に危険です
そんな裂果は手作業で取り除きます。
これも大変な作業ですね
被害を出来るため避けるため、写真のような雨囲いをしています。

雨はブドウ栽培にとって悩みの種です。
着実してから雨が降ると裂果といって実が裂けることがあります。
裂果は着実してすぐと、実が大きくなり色づきだしてからに起こり易いといわれています。
着実してすぐの裂果は裂けた実が自然に落ちて問題ありませんが、実が大きくなり色づきだしてからの裂果は他の実まで腐らすことがあり非常に危険です

そんな裂果は手作業で取り除きます。
これも大変な作業ですね

被害を出来るため避けるため、写真のような雨囲いをしています。
先日、守山市市民講座で「お酒をより美味しく楽しむには?」の題目で講師をしてきました。ブランドなどに惑わされずお金をかけずにお酒を楽しむ法則を披露した所、目からうろこが落ちたと好評でした。実はみんな分かっていることを定義づけてまとめただけだったのです。内容は下の通りです
1、食事やお酒を最高に楽しむには
食事やお酒を最高に楽しむには大きく3つが必要です。
(1)ロケーションlocation
場所(例えば落ち着ける店、景色の良い郊外、いつもの我が家など)
(2)シチュエーションsituation
環境(音楽、サービス、快適な雰囲気、お皿・器やナイフ・フォーク・お箸など、グラスや酒器、料理やお酒の提供温度など)
(3)パーソンperson
人(一緒の時間を共有できて楽しい人)
以上3点は(3)(2)(1)の順で大切ですが、お客や家族を歓待する人で出来ることは(2)のシチュエーション設定です。
2、お酒の温度
お酒を最高に楽しむにはそのお酒に適した温度設定が重要です。この温度設定で感じる美味しさが全然違います。ただ、嗜好には個人差があります。
(1)温度の法則
①甘味は温度が低くなるほど弱く感じる。
②渋み、苦味は温度が低いほど強く感じる。
③酸味は温度が低いほどシャープに感じる。
(お酒の中に多く含まれる有機酸の内、リンゴ酸は低温で美味しく感じ、乳酸は比較的高温で美味しく感じる。)
④フレッシュ感は温度が低いと際立つ。
⑤香りは温度を上げると広がりが大きくなる。
⑥繊細さは温度を上げると抑えられる。
⑦最適温度は人の温度に対する好みと、甘み・渋み・酸味などに関する嗜好から決める。
よく「白ワインは冷やして、赤ワインは常温で」と言われますが、上の法則からすると大まかな事を述べているに過ぎません。例えば渋い赤ワインが好みであれば低温で楽しみ、白ワインが酸っぱすぎる場合は温度を高めに飲むとよいでしょう。また山廃仕込みと呼ばれる日本酒には多く乳酸が含まれていますので、少し高めの温度が良いでしょう。
(2)一般的なサービス温度
①ビール 4~8度(冷蔵庫の温度)
②ワイン
1)スパークリングワイン
8~14度(冷蔵庫、野菜室)
2)甘口白ワイン
8~14度(冷蔵庫、野菜室)
3)辛口白ワイン
8~16度(冷蔵庫、野菜室)
4)ロゼワイン
8~10度(冷蔵庫)
5)軽い赤ワイン
12~16度(野菜室)
6)重い赤ワイン
16~20度(野菜室に2時間ほど入れる)
③日本酒
1)香りの高いタイプ
8~15度(冷蔵庫、野菜室)
2)軽快でなめらかなタイプ
5~10度(冷蔵庫)
3)コクのあるタイプ
15~20度(常温)、40~50度(ぬる燗、熱燗)
4)熟成タイプ
15~25度(常温)、35度(人はだ燗)
3、サービスの順序
人間の舌の感度・感知力は味の慣れによって不確かになり、時間の経過とともに変化するので、お酒をサービスするときには順序が必要です。
・香りのシンプルなものから複雑なタイプへ。
・味の淡麗・軽いものからコクのある複雑・濃厚なタイプへ
・冷たくして味わうものから常温・温めて味わうタイプへ
・新鮮な味わいのものからより熟したタイプへ
・辛口のものからよりうまみの強いタイプへ
・酸味の勝るものから甘味の勝るタイプへ
以上の事を頭に置けば素晴らしいお酒との出会いがあることでしょう!

1、食事やお酒を最高に楽しむには

食事やお酒を最高に楽しむには大きく3つが必要です。
(1)ロケーションlocation

場所(例えば落ち着ける店、景色の良い郊外、いつもの我が家など)
(2)シチュエーションsituation

環境(音楽、サービス、快適な雰囲気、お皿・器やナイフ・フォーク・お箸など、グラスや酒器、料理やお酒の提供温度など)
(3)パーソンperson

人(一緒の時間を共有できて楽しい人)
以上3点は(3)(2)(1)の順で大切ですが、お客や家族を歓待する人で出来ることは(2)のシチュエーション設定です。
2、お酒の温度

お酒を最高に楽しむにはそのお酒に適した温度設定が重要です。この温度設定で感じる美味しさが全然違います。ただ、嗜好には個人差があります。
(1)温度の法則
①甘味は温度が低くなるほど弱く感じる。
②渋み、苦味は温度が低いほど強く感じる。
③酸味は温度が低いほどシャープに感じる。
(お酒の中に多く含まれる有機酸の内、リンゴ酸は低温で美味しく感じ、乳酸は比較的高温で美味しく感じる。)
④フレッシュ感は温度が低いと際立つ。
⑤香りは温度を上げると広がりが大きくなる。
⑥繊細さは温度を上げると抑えられる。
⑦最適温度は人の温度に対する好みと、甘み・渋み・酸味などに関する嗜好から決める。
よく「白ワインは冷やして、赤ワインは常温で」と言われますが、上の法則からすると大まかな事を述べているに過ぎません。例えば渋い赤ワインが好みであれば低温で楽しみ、白ワインが酸っぱすぎる場合は温度を高めに飲むとよいでしょう。また山廃仕込みと呼ばれる日本酒には多く乳酸が含まれていますので、少し高めの温度が良いでしょう。
(2)一般的なサービス温度
①ビール 4~8度(冷蔵庫の温度)
②ワイン
1)スパークリングワイン
8~14度(冷蔵庫、野菜室)
2)甘口白ワイン
8~14度(冷蔵庫、野菜室)
3)辛口白ワイン
8~16度(冷蔵庫、野菜室)
4)ロゼワイン
8~10度(冷蔵庫)
5)軽い赤ワイン
12~16度(野菜室)
6)重い赤ワイン
16~20度(野菜室に2時間ほど入れる)
③日本酒
1)香りの高いタイプ
8~15度(冷蔵庫、野菜室)
2)軽快でなめらかなタイプ
5~10度(冷蔵庫)
3)コクのあるタイプ
15~20度(常温)、40~50度(ぬる燗、熱燗)
4)熟成タイプ
15~25度(常温)、35度(人はだ燗)
3、サービスの順序

人間の舌の感度・感知力は味の慣れによって不確かになり、時間の経過とともに変化するので、お酒をサービスするときには順序が必要です。
・香りのシンプルなものから複雑なタイプへ。
・味の淡麗・軽いものからコクのある複雑・濃厚なタイプへ
・冷たくして味わうものから常温・温めて味わうタイプへ
・新鮮な味わいのものからより熟したタイプへ
・辛口のものからよりうまみの強いタイプへ
・酸味の勝るものから甘味の勝るタイプへ
以上の事を頭に置けば素晴らしいお酒との出会いがあることでしょう!

写真は8月1日現在のヤマ・ソービニオンです
この写真で分かるように、ブドウの実は一度に色づくのではなく、一粒ずつ成熟の度合いが異なります。
成熟度合いを確認しながら収穫の時期を待ちます。

この写真で分かるように、ブドウの実は一度に色づくのではなく、一粒ずつ成熟の度合いが異なります。
成熟度合いを確認しながら収穫の時期を待ちます。
先日、滋賀県守山市主催で「ワイン・日本酒と料理の相性」という題目で講師を行ってきました
数回ワイン講師を行っていますと、多くの人が本当はもっと身近に自由にワインと近づきたいと思っていることがよく分かってきました
なんだかんだ言っても、やっぱりワインはラベルが難しく、開けてみなければ味が分からないという点が一番難点ですね
ラベルからすべての情報を読み取るのはプロでも不可能です。ですからまずは表記の簡単な国産ワインと考える人も多いのですが、日本のワイン表記はずさんで、輸入したブドウジュースを日本で発酵させることで国産ワインとしているので、国産ワインが美味しくないと思っている人が多いのが事実です
私の勤務する酒造メーカーのワインなど、自社畑100%無能薬・有機農法なのに安い値段で頑張っているのに同一に比べられてはたまりません
豊かな人生と経験のためにも、もっと良いワインが身近にあるということを知らせていかなければと思っています

数回ワイン講師を行っていますと、多くの人が本当はもっと身近に自由にワインと近づきたいと思っていることがよく分かってきました

なんだかんだ言っても、やっぱりワインはラベルが難しく、開けてみなければ味が分からないという点が一番難点ですね

ラベルからすべての情報を読み取るのはプロでも不可能です。ですからまずは表記の簡単な国産ワインと考える人も多いのですが、日本のワイン表記はずさんで、輸入したブドウジュースを日本で発酵させることで国産ワインとしているので、国産ワインが美味しくないと思っている人が多いのが事実です

私の勤務する酒造メーカーのワインなど、自社畑100%無能薬・有機農法なのに安い値段で頑張っているのに同一に比べられてはたまりません

豊かな人生と経験のためにも、もっと良いワインが身近にあるということを知らせていかなければと思っています

当社は日本酒、ワイン、リキュールなど多岐にわたり製造していますが、その一つに焼酎があります
滋賀県の酒蔵では米焼酎が主体ですが、当社は米、芋、麦、かぼちゃ、かすとり、あおばながあります
焼酎は原料を醸造したうえで、蒸留を行い、熟成を経て出荷されます
最近人気の本格焼酎での蒸留には、常圧蒸留器を使用する場合と減圧蒸留器を使用する場合がありますが、当社では常圧蒸留器で製造されます
常圧蒸留器とは通常の気圧で蒸留し(蒸留時間が長い)、減圧蒸留器は気圧を下げ(沸点が低いため蒸留時間が短い)、低い沸点で蒸留する方法です。
当然、双方にメリット・デメリットがあります。
・常圧蒸留器
「メリット」・・・原料本来の風味が強く出る。
「デメリット」・・・くせがあると感じる場合がある。
・減圧蒸留器
「メリット」・・・くせがなく飲みやすい。
「デメリット」・・・飲みなれた方には物足りなく感じる。
写真は常圧蒸留器ですが、実際にごらんになった方は少ないと思います。当社訪問の際、お言いつけいただければ見学できますので、是非お越し下さい


滋賀県の酒蔵では米焼酎が主体ですが、当社は米、芋、麦、かぼちゃ、かすとり、あおばながあります

焼酎は原料を醸造したうえで、蒸留を行い、熟成を経て出荷されます

最近人気の本格焼酎での蒸留には、常圧蒸留器を使用する場合と減圧蒸留器を使用する場合がありますが、当社では常圧蒸留器で製造されます

常圧蒸留器とは通常の気圧で蒸留し(蒸留時間が長い)、減圧蒸留器は気圧を下げ(沸点が低いため蒸留時間が短い)、低い沸点で蒸留する方法です。
当然、双方にメリット・デメリットがあります。
・常圧蒸留器
「メリット」・・・原料本来の風味が強く出る。
「デメリット」・・・くせがあると感じる場合がある。
・減圧蒸留器
「メリット」・・・くせがなく飲みやすい。
「デメリット」・・・飲みなれた方には物足りなく感じる。
写真は常圧蒸留器ですが、実際にごらんになった方は少ないと思います。当社訪問の際、お言いつけいただければ見学できますので、是非お越し下さい